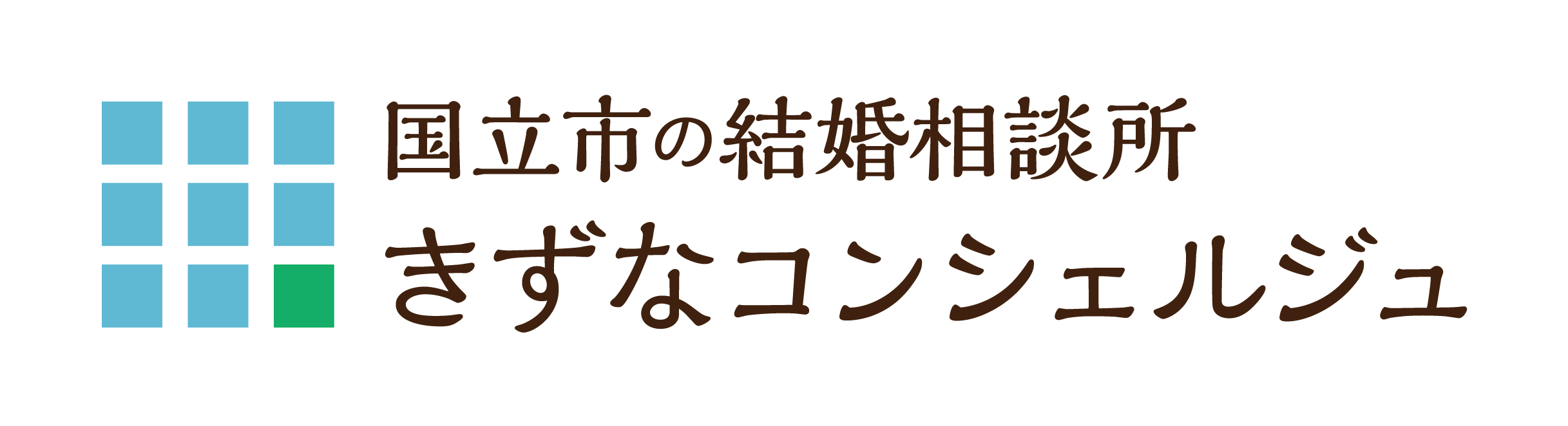数字で見るリアルな婚活!IBJ成婚白書2024徹底分析
こんにちは。
国立市の結婚相談所きずなコンシェルジュです。
今日はIBJが毎年公表している「成婚白書」から読み解く、成婚のポイントを共有させていただきます。
是非ともあなたの幸せなご結婚生活の実現に役立てていただけますと幸いです。
結婚の概況
結婚は人生の大きな節目であり、多くの人にとって幸せを形作る重要な選択肢の一つです 。しかし現代日本では、少子化・未婚化が深刻な社会問題となっています。出生数は過去最少を更新し、婚姻件数も減少傾向が続いています。日本の家族形成においては「結婚」が重視される傾向が強く、婚外子率がわずか2.3%と欧米諸国に比べて極めて低いという特徴があります。このため、婚姻件数の減少が将来的な出生数の低下に直結し、人口減少を加速させる要因となっているのです。
国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、未婚者の約8割は「いずれ結婚するつもり」と考えており、結婚への基本的な意識は昔から大きく変わっていません 。それにもかかわらず、生涯未婚率は上昇の一途をたどり、2020年時点で男性は約28%、女性は約18%に達しています。この背景には、ライフスタイルの多様化、経済的な不安、出会いの機会の減少といった複合的な要因があります。特に若年層はキャリアや自己実現を重視する傾向があり、経済的な不安定さも結婚への障壁となっています 。また、SNSやマッチングアプリの普及により出会いの形は変化しましたが、従来の対面での出会いは減少している現状があります 。これらの要因が絡み合い、結婚を希望しながらも先送りにする人が増えていると考えられます。
このような状況の中で、「結婚を希望する人の意識は変わらないが、現実的な条件や環境の変化により、結婚に至るプロセスが複雑化している」という状況が生まれています。これは単に個人の問題ではなく、社会全体の構造的な課題が背景にあると言えるでしょう。人口動態への複合的な影響も表れており、今後の日本社会の持続可能性に対する懸念が広がっています 。
結婚相談所の「おせっかい」が重要に?
近年、若い世代を中心に結婚相談所の利用が急速に拡大しています。IBJのデータによると、2019年と比較して20代の新規入会者数は約2.5倍、30代は約1.8倍に増加しました(男女計) 。特に男性の伸びが顕著です。この背景には、コロナ禍での出会いの機会の減少 、マッチングアプリ利用者層の拡大とその後の「真剣な出会いを求めて結婚相談所へ移行する」という使い分け・段階的移行、そして結婚・出産のタイミングを計画的に設計したいという“戦略的婚活”意識の高まりなどがあります。効率的かつ信頼性の高い結婚相談所の仕組みが合理的な選択肢となっているのです。
現代の若者は、行動経済学でいう様々な「意思決定の歪み」に晒されやすい状況にあります 。例えば、目先の仕事や遊びを優先して婚活を先送りする「現在バイアス」、居心地の良い現状から離れられない「現状維持バイアス」、結婚という未来を想像しにくい「プロジェクションバイアス」、市場価値の低下リスクを過小評価する「自信過剰バイアス」、過去の交際相手の条件に縛られる「サンクコストバイアス」、結婚後のリスクを過剰に心配しすぎるバイアスなどです。
こうした歪みを自ら修正することは難しいため、他者からの「ちょっとしたおせっかい」、すなわち「ナッジ」が重要になります。かつては親戚や職場、地域社会がナッジの役割を果たしていましたが、現代社会ではその機能が薄れています。そこで、その代わりとして期待されるのが、結婚相談所の「おせっかい力」なのです。結婚相談所のカウンセラー(仲人)によるサポートは、まさに結婚のためのナッジであり、政府や自治体の結婚支援策の中心に据えるべきだと提言されています。
お見合い数の増加も、成婚組数向上に大きく寄与しています。IBJのお見合い数は年々増加し、それに比例して成婚組数も増加しています。主体的な行動や出会いの機会の最大活用が、成婚の可能性を高める根拠となっています。
IBJ成婚者データ分析:リアルな成婚傾向
IBJが公開した「成婚白書」は、日本最大級の婚活会員データベースを分析した結果であり、婚活市場の最新動向や成功事例、具体的な改善策や支援策を示唆するものです。この白書では、IBJ結婚相談所ネットワーク内で成婚退会した15,374名のデータを扱っています。
代表的な成婚者像 2024年の初婚成婚者の代表値(中央値)は、女性34歳、男性36歳でした。活動期間は約9ヶ月(男女合わせた中央値)、交際期間は約4ヶ月と、比較的短期間で意思決定に至っています。これは、一般的な平均交際期間(4.3年)と比較して非常に短い期間です。婚活カウンセラーが間に入ることで、早い段階での価値観の擦り合わせが可能になるためと考えられます。再婚者の場合、活動日数、交際日数ともに初婚者よりさらに短縮される傾向が見られました。
成婚者はお見合い数が多い傾向
成婚者と退会者の違い 成婚者と成婚に至らなかった退会者を比較すると、成婚者は男女ともに退会者より年齢が3~4歳低いことが分かります。また、成婚者は退会者に比べてお見合い数が圧倒的に多い傾向にあります。男性は4倍、女性は2.5倍多くのお見合いを行っています。特筆すべきは、自らお見合いを申し込む「申込数」も成婚者の方が顕著に多い点です。男性は退会者の+21件、女性は+14件多く申し込んでいます。特に男性は、申込数が女性の約2倍である一方、相手からの申受数は女性の約1/3にとどまっており、出会いの機会を得るには自ら積極的に申し込む姿勢が重要と言えます。女性は申受数が申込数を大きく上回る傾向がありますが、自ら申し込むことでより多くの出会いのチャンスを掴める可能性が高まります。
交際移行率の高さ
お見合い数と交際・成婚 成婚者は全年代で10~14回のお見合いを実施し、そのうち4~6人とプレ交際に発展しています。交際移行率は約40%と共通した傾向が見られます。一方、退会者は成婚者より交際移行率が10ポイント以上低い傾向にあります。 成婚までに要する交際日数は、交際およそ150日で6割以上、200日以内に約9割が成婚退会しています。多くのカップルが半年以内に成婚を決断していることが分かります。
年齢
年齢と成婚 年齢層別の成婚率は、男性は30代が、女性は20代~30代前半までが最も高い傾向にあります。40代以降は男女ともに成婚率が顕著に低下します。特に男性の30~34歳は約半数が成婚に至っており、婚活において非常に有利な年代と言えます。女性も30代前半までは高い水準ですが、35歳以降で大きく下がります。若いうちから積極的に取り組むことが、出会いのチャンスを広げ、効率的に結婚へ進みやすくなると考えられます。 成婚相手との年齢差は、男性は年齢が上がるほど相手との年齢差が大きくなる傾向があり、30代は相手の方が-1~3歳下、40代は-4~6歳下となりました。女性はどの年代も相手の方が+2~3歳上の傾向が示されています。男性は年収が高くなるほど、お相手女性との年齢差も大きくなる傾向が見られました。
年収と成婚 男性の場合、全体的に年収が高いほど成婚率が高くなる傾向がありますが、年齢が上がるにつれて成婚率の上昇は頭打ちになります。2024年のデータでは、年収による成婚率の差がコロナ禍前(2017~2019年)よりも緩やかになっており、男性においても「年齢」が成婚の意思決定においてより重要になってきていることが示唆されています。
女性においては、年収に応じた成婚率の差はほとんど見られません。しかし、年代別に見ると、20代は最も高い成婚率(45%~70%)で約2倍成婚しやすいことが示されています。年収公開女性は、お見合いの申受数やお見合い数が約2倍、申込数は3倍も多くなります。年収の水準そのものよりも、情報をオープンにすることが信頼性や安心感に繋がり、成婚率を向上させていると考えられます。
学歴と成婚 男性は学歴が成婚率に大きく影響しており、大卒は高卒より16.8ポイント成婚率が高い結果でした。学歴は「将来の収入や職業の安定性」を示す指標として捉えられることがあるためと考えられます。女性は学歴による差は男性ほど顕著ではありませんが、大卒が最も高い成婚率を示しています。
その他の要素
職業
職業:男性は弁護士が最も成婚率が高く(59.7%)、一般的に高収入とされる職業で高い傾向が見られました。一方、経営者・会社役員、自営業は30%前後にとどまり、安定した職業が重要と示唆されています。女性は介護・福祉関連職が最も高くなりましたが、男性ほど職業による影響は受けにくいようです。女性においても経済的な自立は重要視されており、家事手伝いや定職を持たない場合は成婚率が低い傾向があります。
飲酒
飲酒: 日頃から飲酒習慣がある方が成婚しやすい傾向が見られ、特に男性でその差が顕著でした。適度なアルコールはリラックス効果をもたらし、自己開示が進みやすくなるためと考えられます。
禁煙
喫煙: 男女ともに「吸わない」方が約2倍成婚率が高いことが分かりました。特に女性は喫煙者の成婚率が14.7%と厳しく見られています。
血液型
血液型: 成婚率への影響はほとんど見られませんでした。
婚姻歴
婚姻歴: 男女ともに「初婚」が最も成婚率が高く、「再婚」は約5ポイント低い結果でした。これは再婚者の年齢が高いことが影響していると考えられます。
子供の有無
子供の有無: 男女ともに「なし」が最も成婚率が高く、「あり」の場合は女性で同居か別居かで大きな差が見られました。
続柄
続柄: 「長男・長女」の方が成婚率が高い傾向が見られました。結婚相談所では家族との関わり方について事前に伝える仕組みがあるため、かつての懸念が払拭されやすくなっていると考えられます。
同居希望
同居希望: 自分の家族と同居を「希望しない」方が成婚率が最も高くなりました。活動会員で同居を希望する方はごくわずかです。相手家族との同居希望については、成婚率に大きな差は見られませんでした。
地域による婚活の傾向
地域別に見ると、都市部(北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪、京都、兵庫、広島、福岡)と地方では婚活傾向に違いが見られます。
成婚率
成婚率: 都市部の男性は成婚率が40%を超えて高い傾向にあります。これは都市部に高学歴・高年収の男性が多いことや、女性の都市部への転出による「女性余り」が要因と考えられます。女性は東北・甲信越・東海で30%を超えました。
年齢別傾向
年齢層別傾向: 男性は全年齢層で都市部の成婚率が高い傾向です。女性は都市部では若いほど成婚率が高い傾向が明確ですが、地方では30代前半が最も高く、年齢による成婚率の差が都市部ほど大きくありません。しかし、地方でも40代になると成婚率が大きく低下します。
学歴別傾向
学歴別傾向: 男性は大学院卒、高等専門卒以外は地方の方が成婚率が低く、特に短大卒では16ポイントもの差が見られました。女性は都市・地方ともに大卒が最も高く、次いで大学院卒が高い傾向です。
価値観
価値観・結婚観: 男女ともに「年齢」「性格」「価値観」を重視する点は共通していますが、女性は「年収」を重視する割合が高く、特に都市部の女性で82.6%と最も高くなりました。男性は年収重視の割合は低いですが、「仕事・就業状態」は30%を超えています。外見は男性の方が重視する傾向があり、特に都市部の男性は「顔」を53.3%が重視しています。ワースト項目は男女で異なり、男性は「年収」「身長」「学歴」、女性は「婚姻歴」「身長」「趣味」「家事能力」などでした。外見の中でも「身長」は男女ともにあまり重視されていないことが分かります。
今後の結婚支援と社会的役割
地域における結婚支援は、地域内の成婚促進だけでなく、定住促進や地域経済の活性化にも繋がります。地域特性をふまえた婚活カウンセラーによるサポートが重要です。行政も結婚支援に積極的に取り組んでおり、「伴走型結婚支援」が注目されています。IBJは行政や地域企業と連携し、多様な業種と協力して地域ごとのニーズに応じた結婚支援を拡大しています。例えば、旅行会社である日本旅行も、地域の魅力発信を通じて都市圏の独身者に地域への関心を高め、移住や定住、結婚に繋げる取り組みを行っています。
ただし、人口減少問題の根本的な解決には、結婚支援だけでは不十分です。少子化の原因は結婚数の激減にあるという指摘もあります。地方における若年層、特に20代前半女性の都市部への転出が止まらない状況も、将来の結婚数・出生数を減少させる大きな要因です。これは、雇用の安定化や、地方におけるジェンダーレスな雇用への改革とセットで行わないと、地方の結婚支援が「絵に描いた餅」になりかねないことを示唆しています。
結婚支援の拡大に加え、雇用支援や育児支援、住宅政策の見直し、教育制度の改革など、生活基盤全体を支える社会構造の改革が不可欠です。このような包括的なアプローチがあってこそ、結婚支援の効果が最大限に発揮され、持続可能な社会づくりが実現できると考えられます。
現代の婚活市場はライフスタイルに応じた柔軟な関係性が重視されるなど、急速に変化しています。今後は個々のニーズに応じたパーソナライズ化が進み、より多様な出会いの場が求められるでしょう。結婚相談所は、AIやシステムを活用しつつも、「ヒト」にしかできない意思決定支援を重要視し、カウンセラーの育成を通じて地域仲人基盤を官民連携で構築支援していくことが重要だと考えられます。
まとめ:成婚のポイント
活動量・積極性
- 成婚に至る人ほど積極的に活動しています。
- 成婚者は退会者(非成婚者)に比べて、お見合い数が男性で4倍、女性で2.5倍多いです。
- 自らお見合いを申し込む「申込数」も、成婚者は男性で+21件、女性で+14件多くなっています。
- 男性は出会いの機会を得るために、自ら積極的に申し込む姿勢が重要です(申込数が女性の約2倍に対し、申受数は約1/3にとどまるため)。
- 女性は受け身になりがちですが、自ら申し込むことでより多くの出会いのチャンスをつかめる可能性が高まります。
- 女性の場合、年収を公開している方が非公開の方に比べて約2倍成婚しやすく、お見合いの申受数やお見合い数も約2倍、申込数は3倍多くなります。年収の水準よりも、情報をオープンにすることが信頼性や安心感に繋がり、成婚しやすさにつながると考えられます。
年齢
- 初婚成婚者の代表的な年齢は、女性が34歳、男性が36歳です(中央値)。
- 成婚者は退会者よりも年齢が3~4歳低い傾向が見られます。
- 年齢層別の成婚率は、男性は30代が最も高く、女性は20代~30代前半までが最も高いです。
- 40代以降になると男女ともに成婚率は顕著に低下します。若いうちから積極的に婚活に取り組むことが、出会いのチャンスを広げ、効率的に結婚へ進みやすくなります。
- 男性の年収区分別に見ると、年収が高くなるほどお相手女性との年齢差も大きくなる傾向が見られます。
- 男性の成婚率において、全体的に年収が高いほど成婚率が高くなる傾向がありますが、年齢が上がるにつれて成婚率の上昇は頭打ちになり、年齢による影響も十分に考慮する必要があります。男性も年齢を意識して活動をスタートさせることが重要です。
- 女性においては、年収に応じた成婚率の差はほとんど見られませんが、年代別に比較すると年齢が上がるにつれて成婚率が低下する傾向が見られます。女性の成婚率に影響を与える要因としては、年収よりも年齢の方が大きいと考えられます。
活動期間・交際期間
- 成婚者の在籍日数は約9か月(男女合わせた中央値)、交際日数は約4か月と、比較的短い期間で意思決定しています。
- 再婚者は初婚者よりも活動日数、交際日数ともに短くなる傾向があります。
- 多くのカップルが交際およそ150日(約5か月)で6割以上、200日(約6.5か月)以内に約9割が成婚退会しており、半年以内での決断が多いことを示しています。交際200日以降は成婚率の上昇がほとんど見られないため、交際半年がポイントとなる可能性があります。
条件面(年収・学歴・職業・価値観)
- 男性の学歴は成婚率に大きく影響し、大卒が高卒より16.8ポイント成婚率が高いです。学歴は「将来の収入や職業の安定性」を示す指標として捉えられることがあります。女性は男性ほど顕著ではありませんが、大卒の成婚率が最も高いです。
- 男性の職業では、弁護士(59.7%)など一般的に高収入と言われる職業で成婚率が高い傾向が見られます。経営者・会社役員、自営業は成婚率が30%前後にとどまることから、安定した職業であることも重要であると示唆されています。
- 女性の職業による成婚率への影響は男性ほど大きくありませんが、家事手伝いや定職を持たない場合は成婚率が低い傾向にあり、経済的な自立が重要視されていることがうかがえます。
- 結婚相手に求める条件として、男女ともに「年齢」「性格」「価値観」が共通して重視されています。
- 女性は「年収」も重視する割合が高く(都市部82.6%、地方74.1%)、男性は「仕事・就業状態」(30%超)を重視する傾向があります。
- 男性は「顔」や「体型」など外見を重視する傾向があり、特に都市部の男性は「顔」を重視する割合が過半数を超えています。女性は外見の優先度は中程度以下です。
- 外見の中でも「身長」は男女ともにそれほど重視されていません。
心理的側面・サポート
- 現代の若者は、目先の仕事や遊びを優先して婚活を先送りする「現在バイアス」、居心地の良い独身生活から離れられない「現状維持バイアス」、結婚という未来が想像しづらい「プロジェクションバイアス」、市場価値低下のリスクを過小評価する「自信過剰バイアス」、過去の交際に縛られる「サンクコストバイアス」、結婚後のリスクを過剰に心配する「確率加重関数によるバイアス」など、行動経済学的な意思決定の歪みに晒され、婚活に失敗することがあります。
- また、多くの情報・選択肢へのたじろぎ(選択過剰負荷、情報過剰負荷)や、低賃金・長時間労働による意志力の低下も障壁となります。
- これらの歪みを是正するためには、自分では気づきにくい自らの状況に対し、他者によるちょっとした「おせっかい」、すなわち「ナッジ」が非常に重要です。
- 昔の社会では親戚や職場などがナッジの役割を果たしていましたが、現代ではその機能が低下しており、その代替として結婚相談所による「おせっかい力」(仲人サポート)が期待されています。
- 仲人サポートは結婚のためのナッジであり、結婚支援策の中心に据えるべきだと考えられています。婚活カウンセラーが間に入り価値観の擦り合わせを行うことで、早い段階での意思決定につながります。
地域性
- 都市部の男性は地方に比べて成婚率が高い傾向にあります。これは都市部に高学歴・高年収の男性が多いことや、女性が都市部へ転出し「女性余り」の状態となりやすいことが背景に挙げられます。
- 女性の場合、都市部では年齢が若いほど成婚率が高い傾向が明確ですが、地方では30代前半の成婚率が最も高く、都市部女性ほど年齢の影響を強く受けにくい傾向があります。ただし、40代以降は地方でも成婚率が大きく低下します。
- 地方では、男性の学歴別成婚率が都市部より低い傾向が見られます(特に短大卒)。
- 結婚相手に求める条件など、婚活者の価値観や結婚観にも地域差が見られます。
- 地域に根差した結婚支援として、地域特性をふまえた提案やサポートが成婚への後押しとなります。行政や自治体、民間企業が連携した地域社会全体での結婚支援(共助)の強化が期待されています。